
2025.03.04 社内報制作の基礎
| 優秀賞 | 季刊(グループ報) | まど | サントリーホールディングス株式会社 |
| 総合賞 | 月刊(単独社内報) | キヤノンライフ | キヤノン株式会社 |
| HUMAN ENERGY COLORS | 中部電力株式会社 | ||
| 月刊(グループ報) | 月刊かもめ | 株式会社リクルートホールディングス | |
| 隔月刊(単独社内報) | JFEスチールマガジン | JFEスチール株式会社 | |
| 隔月刊(グループ報) | ALUMINIST | 株式会社UACJ | |
| 季刊(単独社内報) | ひかり | 近畿日本鉄道株式会社 | |
| さんげつ | 株式会社サンゲツ | ||
| TG TIMES | 豊田合成株式会社 | ||
| 季刊(グループ報) | Spark | 積水化学工業株式会社 | |
| DNP Family | 大日本印刷株式会社 | ||
| KITCHEN OF THE EARTH | 日清食品ホールディングス株式会社 | ||
| はぁもにぃ | 株式会社ファンケル | ||
| M-SPIRIT | 丸紅株式会社 | ||
| 企画賞 | 月刊(単独社内報) | Shuttle | トヨタ紡織株式会社 |
| 隔月刊(単独社内報) | &you | 三井不動産株式会社 | |
| 隔月刊(グループ報) | 敬天愛人 | 京セラ株式会社 | |
| 季刊(単独社内報) | 奏 | 三菱UFJニコス株式会社 | |
| 季刊(グループ報) | アメイジングファクトリー! | 明治ホールディングス株式会社 | |
| ROOM | 株式会社りそなホールディングス | ||
| 奨励賞 | 月刊(単独社内報) | FAMILY | 株式会社ファミリーマート |
| 月刊(グループ報) | Fe World | 富士電機株式会社 | |
| 季刊(単独社内報) | 西松人 | 西松建設株式会社 | |
| 季刊(グループ報) | Loop | カルビー株式会社 | |
| 飛翔 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | ||
| SHIN | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 優秀賞 | MBK LIFE | 三井物産株式会社 |
| 総合賞 | act | 株式会社アイシン |
| KIRIN Now | キリンホールディングス株式会社 | |
| web-ism | 株式会社西武ホールディングス | |
| NSL+ | 日鉄物流株式会社 | |
| comMS | 三井住友海上火災保険株式会社 | |
| 企画賞 | パナソニックグループ コミュニケーションマガジン「幸せの、チカラに。」 | パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社 |
| MCIねっとonline | 三井化学株式会社 | |
| 奨励賞 | Ripple Workers Index | オプテックス株式会社 |
| SUBAROOM | 株式会社SUBARU | |
| YANMER FESTIVAL 2023 ~Beyond~ | ヤンマーホールディングス株式会社 |
| 優秀賞 | ブランド・ライブ ブランド・ライブ2024 |
住友生命保険相互会社 |
| 総合賞 | NextageHeadline お客様・地域社会の課題解決への取り組み |
東京海上日動火災保険株式会社 |
| 企画賞 | エレベーターサイネージ報 第1弾「Big Many賞 応募受付開始!」 |
関西テレビ放送株式会社 |
| webEAST 「特集」NTT東日本グループ 「私たちはここから、アジアのミライをつなぐ」 ~NTT e-MOI Concept Movie~ |
東日本電信電話株式会社 | |
| 奨励賞 | V-Studio 社長と従業員の対談型のトーク型番組の映像社内報シリーズ |
株式会社ビジョン |
先日、「経団連推薦社内報審査」の審査結果が届きました。「雑誌・新聞型社内報部門」に応募したのですが、残念ながら受賞には至りませんでした。審査員による講評を参考にしながら、また次回に向けて改善していきたいと思っています。受賞作品の傾向と対策のようなものがあれば教えていただきたいです。

経団連推薦社内報審査は、1966年から毎年開催されている歴史ある審査で、その受賞を一つの指標にして、社内報制作に臨む担当者も多いのではないでしょうか。毎年9月に応募が締め切られ、2月に審査結果が発表されます。日ごろ一生懸命制作している社内報に対して、経団連という客観的な外部の視点によって評価される機会は貴重でしょう。
私たちも社内報制作をお手伝いする中で、これまでも社内報担当者より受賞の連絡を受け、一緒に喜びを分かち合うことが多くありました。受賞の中には、最優秀賞、優秀賞、総合賞などがあります。今回、受賞作品を含め、さまざまな企業の社内報を見てきた太平社のディレクター陣による意見交換を実施しました。そこで出た「受賞作品から見えるグッドポイント」を5つにまとめてご紹介します。
目次
まず「受賞作品」と「それ以外の作品」を比較して感じる大きな違いは、テーマ設定力と言えるでしょう。受賞している作品は、企画テーマ、言い換えると、企画を一言で表すタイトルだけで興味を掻き立てられます。貴社の社内報誌面に踊るタイトルを見て、読者はワクワクするでしょうか。
ただ「プロジェクトに迫る」や「社長が語った経営方針」などでは難しいでしょう。プロジェクトで発揮された社内の強みを表すキーワードや、社長講話の中で最も伝えたかったポイントを抜き出して、テーマに設定し、タイトルで表現できている社内報が受賞作品には多いと思います。何について読者と考えたいのか、そのテーマが明確で引き付けるものになっているかどうかがポイントと言えます。
実際に経団連社内報審査基準の中にも、「企画の狙いが明確」「魅力的な企画」「独自性や進取性」といったポイントが明記されています。テーマ設定はそんなに難しいことではありません。中期経営計画の中のキーワードから発想を広げてみたり、社内で最近飛び交っている用語に着目してみたり、社員たちが自分たちらしさとして自然と認識している会社の個性を取り上げてみたり。そんなところから、社員の興味を喚起する、貴社独自のテーマが生まれてくるはずです。
多くの企業の社内報を見ていると、一つひとつの企画が短絡的でこま切れになっていて、チラシを集めて綴じたような印象の社内報が多いことに気づきます。社長挨拶文をそのまま掲載したり、部署紹介や活動レポートの寄稿文をそのまま掲載したり。
受賞作品には、そうした単発の企画ページの寄せ集めだけでなく、一つのテーマに対してさまざまな視点からページを展開させている特集が多いです。それこそがまさに「雑誌・新聞型社内報」の特長を生かした発信術と言えるでしょう。
例えば、自分たちの働き方について考えてもらうための企画を作る場合。ただ自社の制度紹介だけでいいでしょうか。社長や担当役員から社員に呼び掛けるだけでいいでしょうか。そのような短絡的な企画だけで終わらせず、経団連社内報審査基準の中にも「多面的で説得力のある展開」とあるとおり、さまざま視点から「働き方」を考えるきっかけを投げかける誌面を作ることが重要です。
例えば、展開案として一例を挙げてみると。
テーマに対して、該当する本人、その先輩後輩同僚、経営層、社外の有識者、その他の社員など、さまざまな立場の人に、何をどんな形式でコメントしていただくかを考え、展開していく誌面づくりを意識することが大切でしょう。
これもよくあることなのですが、「社内報のリニューアル」や「制作メンバーの変更」の節目で検討したはずの編集方針が、いつの間にか忘れ去られていることはないでしょうか。毎号の制作に追われると、社内報を発行する目的や編集方針に立ち返って、判断していくことが難しい実情も理解できます。
そうした陥りがちな状況を見抜いてなのか、経団連社内報審査基準の中の最も高い配点項目欄に「発行目的」「編集方針」というポイントが入っています。当然ながら、社内報は決まった目的のために作られるもの。自社の状況を踏まえて、目的や方針をきちんと決め、言語化しておく必要があります。
その後、毎号の企画会議の際にメンバー間で確認し合ったり、台割表や制作スケジュール表の中に明記しておくなど、常にメンバーで意識しながら進行する工夫も一手かもしれません。実際に、太平社がお手伝いする受賞作品の制作現場では、判断に迷った際に、編集方針に立ち返って検討するケースが多く見られます。
いろんな社内報の誌面を見ていると、大きく分けて2種類の作り方があることが見えてきます。原稿や写真、図表などの構成要素を準備してから、それを決められたページ内に収まるように詰め込んでいるパターン。初めに誌面構成ラフを描き、検討したうえで、それに合わせた原稿や写真、図表を準備するパターン。
受賞作品は圧倒的に後者の手法で作られていることが多いと感じます。そうすることによって、適切な文字量・文字サイズの見出しや本文が配置でき、企画を上手に演出する写真やイラストなどのビジュアルを印象的にレイアウトできているのです。
この作り方は、読者に伝わりやすい誌面づくりに直結します。それと同時に、制作メンバーにとっても、共通の完成誌面を先にイメージしたうえで準備に取り掛かれるので、効率的な制作フローとも言えます。しかも、社内報担当者のやるべきことはシンプル。制作会社に誌面構成ラフの提案をお願いし、それを事前に確認したうえで、準備に取り掛かるだけです。今日からぜひやってみてください。
最後に挙げる、受賞作品から見えるポイントは、「発行元企業の社内報担当者が担う役割」と、「社内報のプロである制作会社が担う役割」をきちんと分担している点です。無理な負担がないよう、上手に連携している制作チームが受賞作品を生み出しているように感じます。それぞれが担うべき主な役割の一例を挙げてみると。
社内報担当者の主な役割
制作会社の主な役割
社内報担当者にしかできない領域と制作会社に任せた方が効率的で高品質になる領域を自社の都合に合わせて見極めましょう。継続して発行できるような体制を予算に合わせて構築することが大切です。
いかがでしたでしょうか。日ごろから社内報制作のお手伝いをしているディレクター陣が、「受賞作品から見えるグッドポイント」を5つにまとめてみました。社内報改善のヒントにしていただけると嬉しいです。

関連リンク SHARE広報担当者向け情報誌「SHARE」のvol.07とvol.08には、受賞作品を制作する企業のご担当者様へのインタビュー記事を掲載。無料で読めますので、ぜひ参考に。
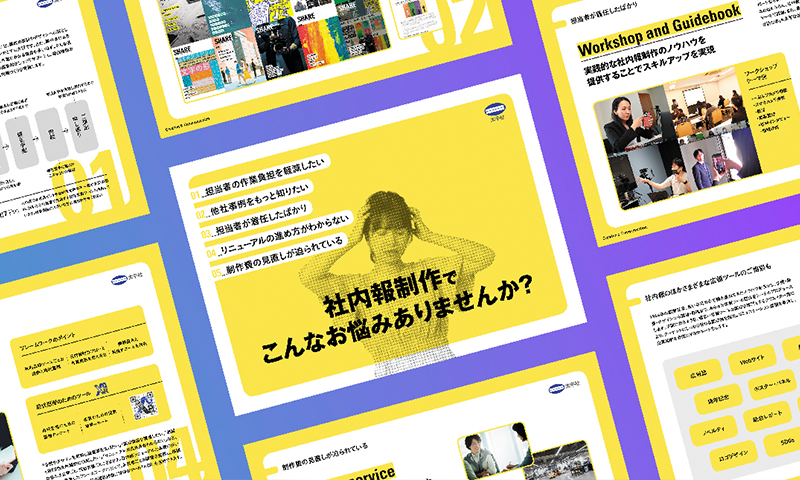
関連リンク 社内報制作サービスガイドブック長年、多くの企業の社内報制作をサポートしてきた太平社が持つノウハウを提供し、社内報担当者の皆さんのお役に立てるよう、資料を公開します。
また、社内報に限らず、さまざな広報ツール制作における「お悩み相談」も受付中です。どんなお悩みでも結構です。頂いたお悩みについては、コラム記事などで今後も回答していきたいと思いますので、お気軽に下記よりお寄せください。